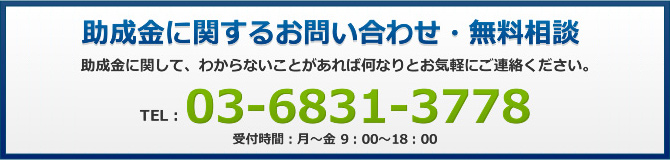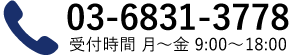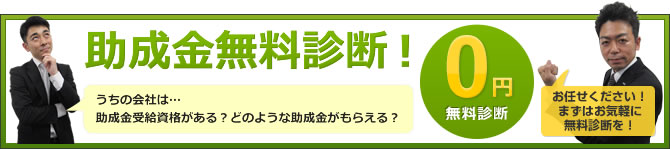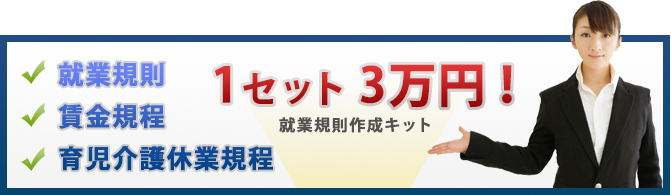【社労士が解説】中小企業が知っておくべきカスタマーハラスメント(カスハラ)対策とは?|従業員を守り会社のリスクを減らすために
更新日:2025/07/08
労務管理

近年、働く人々のメンタルヘルス対策の重要性がますます高まっています。特に、長時間労働や職場のハラスメントなどが原因で精神的な不調を抱える労働者が増加している状況を踏まえ、労働安全衛生法等の改正が進められています。
これまで従業員数50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェック制度ですが、2025年5月に改正労働安全衛生法案が可決され、今後従業員数50人未満の事業場にも義務化される見通しとなりました。これは、多くの中小企業にとって、新たな対応が求められる重要な変更点です。
本コラムでは、中小企業におけるストレスチェック義務化について、その背景や制度の概要、企業が直面しうる課題、そして今から準備すべき対応策について、提供されたソースに基づいて詳しく解説します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?中小企業も無関係ではない理由
近年、ニュースなどでも取り上げられることが増えた「カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)」。顧客や取引先が、その立場を利用して、相手先の企業や従業員に対し理不尽な要求を行う行為を指します。全てのクレームがカスハラではありません。商品やサービスの改善を求める正当なクレームとは区別されます。
「大企業だけの問題だろう」と思われる中小企業の経営者様もいらっしゃるかもしれません。しかし、カスハラは個人のお客様だけでなく、取引先からの行為も含まれます。そのため、業種や企業規模を問わず、どの企業もカスハラの被害に遭う可能性があります。厚労省の調査では、過去3年間にハラスメントを受けた従業員の割合で、カスハラが2番目に多かったという結果も出ています。
カスハラは従業員にとって大きなストレスとなり、心身の不調、さらには休職や離職につながることもあります。従業員が安心して働ける職場環境を維持するためにも、カスハラ対策は中小企業にとっても非常に重要な課題なのです。
どこからがカスハラ?その判断基準
カスハラの判断基準は、法令などで具体的に定められているわけではありません。そのため、企業は自社で判断基準を明確にし、従業員に周知しておくことが求められます。
判断する上での考え方の一つとして、以下の2つの観点があります。
- ① 顧客や取引先の要求内容に妥当性があるか 自社のサービスに過失があったり、商品に欠陥があったりする場合の改善要求は正当なクレームです。しかし、事実に基づかない要求や、確認しても自社に過失が見られない場合の要求には妥当性がないと判断されます。
- ② 社会通念上不相当な言動か たとえクレーム内容に妥当性があったとしても、要求が行き過ぎていたり、従業員の就業環境を著しく害するような言動はカスハラと判断されます。例えば、暴言や脅迫、長時間に及ぶ、あるいは執拗に繰り返されるクレームなどがこれにあたります。これらの行為は、状況によっては傷害罪や脅迫罪など、法令に抵触する可能性もあります。
重要なのは、単に要求内容だけでなく、その「言動」も判断基準となる点です。
カスハラが会社と従業員にもたらす被害
カスハラは、被害を受けた従業員の心身の健康に深刻な影響を与えます。大きなストレスは、精神的な不調だけでなく、身体的な不調の原因ともなり得ます。その結果、休職や退職を選択せざるを得なくなる従業員も少なくありません。これは、中小企業にとって優秀な人材の流出という大きな損失につながります。
さらに、カスハラが発生しているにも関わらず、企業が適切な対策を講じなかった場合、安全配慮義務違反と判断される可能性があります。安全配慮義務とは、使用者が労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をする義務のことです(労働契約法第5条)。カスハラに対して何もしないと、この義務を果たしていないとみなされ、被害を受けた従業員から損害賠償を請求されるリスクも発生します。実際に、企業に賠償責任が認められた裁判例も存在します。
また、2023年9月からは、精神疾患の労災認定基準が見直され、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」という項目が追加されました。これは、カスハラが業務による心理的負荷となり、精神疾患の発症原因となり得ることを示すものであり、企業はより一層、カスハラ対策に取り組む必要性が高まっています。
中小企業が今すぐ取り組むべきカスハラ対策のポイント
カスハラ対策は、発生してしまった時の対応だけでなく、日頃からの予防が非常に重要です。従業員を守ることは、企業自身を守ることにもつながります。中小企業でも取り組みやすい対策のポイントをいくつかご紹介します。
- カスハラ対策の基本方針や姿勢を明確にする:企業として「カスハラには屈せず、従業員を全力で守る」という毅然とした姿勢を明確に示しましょう。これにより、従業員は安心して働くことができるようになります。
- カスハラの発生時の対応方法や手順を決めておく:実際にカスハラが発生した際に、現場の従業員がどのように対応すれば良いか、具体的な方法や手順を社内ルールとして定めておきましょう。対応マニュアルを作成することも有効です
- 相談体制を整備する:カスハラに関する相談を受け付け、迅速かつ適切に対応できる窓口を設置します。2020年に設置が義務化されたパワーハラスメントの相談窓口で、カスハラの相談を受け付けられるように体制を整える方法もあります。相談窓口の担当者は、事実関係の把握や被害者への配慮など、慎重な対応が求められます。
- 従業員への教育、研修を実施する:従業員に対し、カスハラに関する正しい知識や、会社が定めた対応ルール、相談窓口の存在などを定期的に周知徹底しましょう。また、自社の従業員が知らず知らずのうちに取引先へカスハラ行為を行わないよう、加害者側にならないための教育も重要です。
- 被害を受けた従業員への配慮を行う:カスハラの対応を特定の従業員だけに任せず、複数名や組織として対応にあたりましょう。また、被害を受けた従業員のプライバシーに配慮し、心身のケアを最優先することも大切です。
- 再発防止への取り組みを継続する:一度対策を講じたら終わりではなく、定期的に社内体制やルールを見直し、改善を続けることが重要です。
社内だけで対応が難しい場合や、取引先との関係が複雑なケース、法令に抵触する可能性のあるケースなど、外部との連携も視野に入れる必要があります。弁護士や警察への相談も有効な手段となり得ます。
カスハラ対策を進めるメリット
カスハラ対策に積極的に取り組むことは、従業員だけでなく企業にも多くのメリットをもたらします。
- 従業員の安心感向上と定着率アップ:会社が従業員を守る姿勢を示すことで、従業員は安心して業務に集中できます。これにより、離職を防ぎ、優秀な人材の定着につながります。
- 会社のリスク低減:安全配慮義務違反や損害賠償請求のリスクを回避できます。また、悪質なカスハラ行為を行う顧客や取引先への対応を明確にすることで、トラブルの拡大を防ぐことにもつながります。
- 企業イメージの向上:従業員を大切にする企業であるという姿勢は、対外的にも良いイメージを与えます。
実際にカスハラ対策に取り組んでいる企業からは、「落ち着いて対応できるようになった」「安心して働けるようになった」といった従業員の声や、「好ましくない顧客が来にくくなった」といった企業側の声も聞かれます。
カスハラ対策でお困りではありませんか?【日本社労士法人】にご相談ください

カスハラ対策は、企業の規模に関わらず、従業員が安心して働くために、そして企業自身がリスクを回避するために不可欠です。しかし、「何から始めたら良いか分からない」「社内だけでの対応に限界を感じる」といったお悩みを抱えている中小企業様もいらっしゃるかもしれません。
日本社労士法人では、中小企業の状況に合わせたカスハラ対策のコンサルティングや、社内規程の整備、従業員研修の実施、相談窓口設置のサポートなどを行っております。貴社の従業員を守り、円滑な事業継続を支援するための最適な対策をご提案いたします。
カスハラ対策についてご不明な点やご心配な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
個別相談・お問い合わせはこちらから