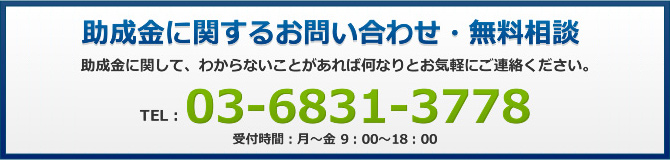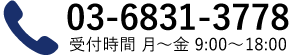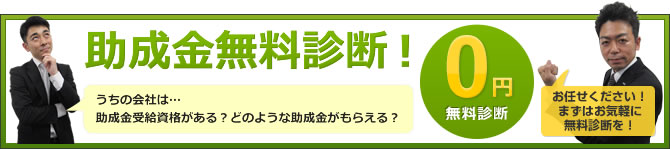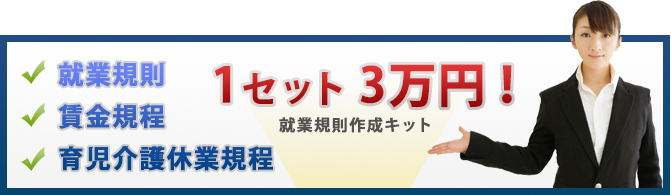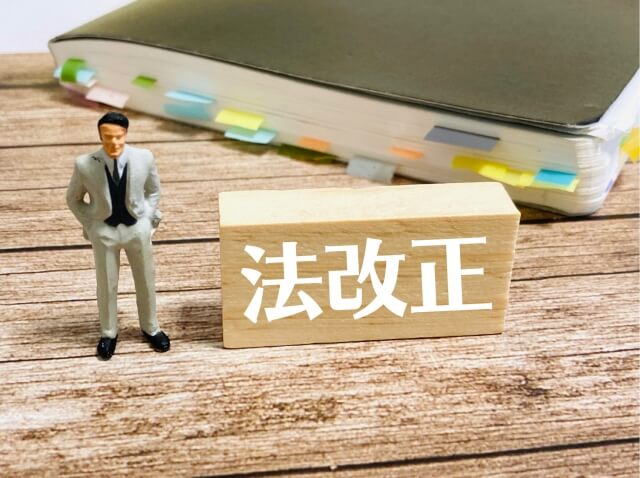【中小企業向け】返済不要の助成金で事業成長!メリット、おすすめ3選、申請サポートガイド
更新日:2025/05/20
助成金

「助成金」は、事業の課題解決や成長を後押しする強力なツールです。特に中小企業にとって、返済不要な資金は大きな魅力となります。このガイドでは、助成金活用のメリットや、多くの企業が活用しやすいおすすめの助成金を原生してご紹介します。貴社の「働き方改革」「人材育成」「雇用改善」といった取組に是非お役立てください。
はじめに:助成金とは?
「助成金」と聞くと、「手続きが難しそう」「うちの会社には関係ないのでは?」と思われる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、助成金は返済不要な公的資金であり、適切に活用することで、貴社の経営課題の解決や事業のさらなる発展を強力に後押ししてくれます。
特に、働き方改革の推進、従業員のスキルアップ、多様な人材の雇用促進といった現代の企業経営において重要なテーマに取り組む際に、助成金は大きな力となります。このガイドでは、中小企業の皆様が取り組みやすい、特におすすめの助成金を厳選してご紹介します。
助成金を活用するメリットとは?
助成金を活用することには、様々なメリットがあります。
- 新たな投資へのハードルが下がる:設備投資や人材育成、雇用環境の整備など、ホウライであれば大きな費用が掛かる取り組みに対し、助成金が費用の一部をカバーしてくれるため、計画を実行に移しやすくなります。
- 資金繰りの改善に貢献:返済の必要がない資金が増えることで、手元資金に余裕が生まれ、資金繰りの安定化につながります。
- 従業員の定着率向上や意欲向上:労働時間短縮や年次有給休暇の取得促進、賃金アップ、スキルアップ支援、育児・介護との両立支援などに取り組むことで、従業員の満足度やモチベーションが高まり、離職率の低下や生産性の向上に繋がります。
- 企業イメージの向上:働きやすい環境づくりや、法令遵守への積極的な取り組みは、企業の信頼性やブランドイメージを高め、優秀な人材の確保にも有利に働きます。
- 経営課題の解決:助成金の要件を満たすために経営計画を見直したり、専門家のアドバイスを受けたりする過程で、自社の課題が明確になり、その解決に繋がります。
中小企業におすすめ!使いやすい助成金3選
様々な助成金がある中で、多くの中小企業様にとって比較的取り組みやすく、大きなメリットが期待できる助成金を3つご紹介します。
1. キャリアアップ助成金(正社員化コース)
この助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者を、正社員(多様な正社員を含む)に転換または直接雇用した場合に助成される制度です。
なぜおすすめ?
非正規雇用の従業員を正社員として雇用することは、授業院のモチベーション向上や定着に直結し、企業の組織力強化に繋がります。多くの企業に非正規雇用の従業員がいらっしゃるため、検討しやすい助成金の一つです。
助成額(中小企業の場合)
- 有期雇用から正規雇用へ転換:1人あたり最大80万円(1期40万円、2期40万円)(注:支給対象期間は1年間のうち、最初の6ヶ月を第一期、次の6ヶ月を第二期と呼びます)
- 無期雇用から正規雇用へ転換:1人あたり最大40万円(1期20万円、2期20万円)(注:上記「有期→正規」の()内の金額は大企業の助成額です)
- 正社員転換制度を新たに規定して転換した場合:1事業所あたり1回限り20万円加算(注:大企業の場合は15万加算)
- 多様な正社員制度(勤務地限定、職務限定、短時間正社員)を新たに規定して転換した場合:1事業所あたり1回限り40万円加算(注:大企業の場合は30万円加算)
主な要件
- 雇用保険や社会保険(加入義務がある場合)に加入している事業所であること。
- 6ヶ月以上在籍している正社員以外の労働者を雇用していること。
- 就業規則等に転換制度を新たに規定し、労働基準監督署に届け出ていること。
- 転換予定日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、届け出ていること。
- 正社員に適用される就業規則に「賞与または退職金」かつ「昇給」が規定・運用されていること。
- 転換前後6ヶ月の賃金を比較して3%以上増額していること。
- 転換日前後6ヶ月以内に事業主都合による解雇等をしていないこと。
(注)支給申請上限人数は1年度1事業所あたり20人までです。令和7年4月1日以降は、重点支援対象者(雇入れから3年以上経過した有期雇用労働者など)のみ2期目の支給対象となる場合があります(ソース外情報)。
2. 業務改善助成金
この助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図り、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に対して、その費用の一部を助成する制度です。
なぜおすすめ?
最低賃金の上昇は多くの事業場に影響がありますが、この助成金を活用することで賃上げにかかる負担を軽減できます。さらに、賃上げと同時に業務効率化に繋がる設備投資も支援されるため、生産性向上と労働条件改善を同時に進めることが可能です。
助成額
引き上げる労働者数や引上額に応じて助成上限額が変わります。例えば、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内 かつ 常時使用する労働者数30人未満の事業場 の場合、10人以上の労働者の賃金を90円以上引き上げると、最大で600万円の助成上限額が設定されています。
助成率は、事業場内最低賃金が1000円未満の場合は4/5、1000円以上の場合は3/4となります。10人以上の上限額区分は、特例事業主(事業場内最低賃金が1000円未満または物価高騰等の影響を受けた事業主)が10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象となります。
主な要件
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること。
- 中小企業・小規模事業者であること。
- 解雇や賃金引下げなどの不交付事由がないこと。
- 事業場内最低賃金を30円以上引き上げること(コースによって引上額の最低基準が異なります)。
- 生産性向上に資する設備投資などを行うこと。
対象経費の例
POSレジシステムの導入による在庫管理時間の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮など。PCやスマートフォン本体は原則対象外ですが、特例事業主の場合は対象になる場合があります。
3. 人材開発支援助成金
この助成金は、労働者に専門的な知識・技術を習得させるためのOFF-JT(OJTと区別して行われる訓練)を10時間以上行った場合に助成されます。
なぜおすすめ?
従業員のスキルアップは、変化の激しい現代において企業の競争う力を維持・向上させるために不可欠です。この助成金を利用すれば、外部研修の受講費用や研修期間中の賃金の一部が助成されるため、従業員の能力開発を計画的に進めることができます。
助成額(中小企業の場合)
- 経費助成:OFF-JT訓練に要した経費の45%(正規雇用労働者)または70%(有期雇用労働者)。賃金要件または資格等手当要件を満たす場合はさらに15%加算されます。1労働者1訓練あたりの経費助成限度額は、実訓練時間数に応じて10時間以上100時間未満で15万円、100時間以上200時間未満で30万円、200時間以上で50万円です。
- 賃金助成:OFF-JT訓練実施中の賃金について、1人1時間あたり800円(正規雇用労働者・有期雇用労働者)。賃金要件または資格等手当要件を満たす場合はさらに200円加算されます。
- OJT実施助成:認定実習併用職業訓練(OJTとOFF-JTの組合せ)の場合、1人1コースあたり20万円。賃金要件または資格等手当要件を満たす場合はさらに5万円加算されます。
主な要件
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 職務に関連した専門的な知識・技術を習得させるためのOFF-JT訓練(実訓練時間数10時間以上)であること。
- 訓練開始日の1か月前までに、訓練内容等を記載した「訓練計画届」を提出すること。
計画提出前1年間に他の訓練の申請があった場合の離職率判定が追加されました。
有期契約労働者等を正社員に転換するための訓練(有期実習型訓練)もあります。計画時の審査が廃止となり「受付」のみとなり、申請時の審査となります。
助成金申請は専門家へお任せください
助成金の制度は多岐にわたり、要件や申請手続きが複雑な場合があります。計画書の作成、必要書類の準備、申請期間の管理など、不備なく行うためには専門的な知識が不可欠です。
日本社会保険労務士法人は、助成金の専門家として、貴社の状況に合わせた最適な助成金の提案から、複雑な申請手続きの代行まで、トータルでサポートいたします。
「どの助成金が利用できるのか分からない」「申請書類の作成が難しい」「本業が忙しくて手続きに時間を割けない」といったお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。助成金活用のプロが、貴社の事業成長をしっかりとお手伝いいたします。
お問い合わせはこちら

助成金に関するご相談、お問い合わせは、お気軽に日本社会保険労務士法人までご連絡ください
お問合せ:https://nsrh.jp/contact.html
専門家へのご相談で、貴社にとって最適な助成金を見つけ、スムーズな申請を実現しましょう。
ご注意
助成金の要件や内容は、制度改正等により変更される場合があります。本コンテンツは2025年4月時点の情報に基づいています。最新の情報や詳細については、必ず厚生労働省のウェブサイトや、弊社へご確認ください。
また、助成金の支給には審査があり、申請すれば必ず受給できるものではありません。
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
見出し1