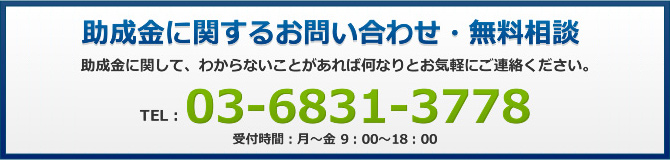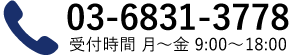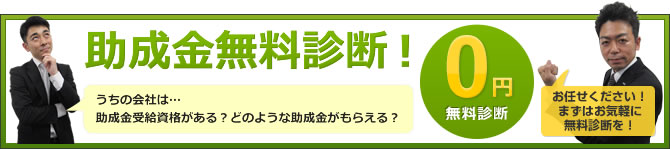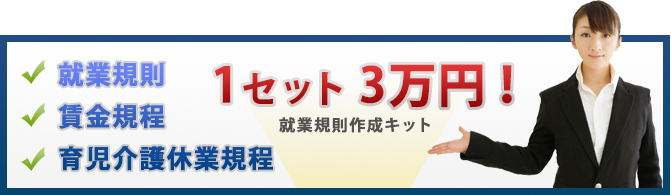【2025年10月義務化】3歳~就学前の子を持つ社員への新制度!「養育両立支援休暇」導入のすべて
更新日:2025/11/07
法改正

2025年10月1日より、育児・介護休業法が改正され、3歳から小学校就学前の**子どもを養育する従業員に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」**の導入が義務化されます。
この措置の選択肢の一つとして新設されたのが「養育両立支援休暇」です。企業が優秀な人材の離職を防ぎ、定着率を向上させるためにも、この新しい休暇制度について深く理解し、円滑に導入を進めることが急務となっています。
今回は、この養育両立支援休暇の制度内容から、導入の進め方、そして実務上の重要なポイントについて、社会保険労務士の視点から解説します。
養育両立支援支援制度とは?(2025年10月施行の背景)
育児・介護休業法は、2025年4月1日以降、段階的に施行され、仕事と育児・介護の両立を支援する制度の拡充が進められています。
その流れの中で、2025年10月1日の改正により、企業は3歳から小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日)の子どもを養育する従業員に対し、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じることが義務付けられました。
養育両立支援休暇は、事業主が講じるべきこの「柔軟な働き方を実現するための措置」として用意された5つの選択肢の中の一つです。仕事と育児を両立しやすくするために創設された休暇であり、導入すれば、従業員は保育所の送迎や学校行事、就学予定の小学校の下見など、用途を限定されずに休暇を取得できます。
導入時に確認すべき制度の要件
養育両立支援休暇は、上記5つの措置から企業が任意で選択できる制度です。もし、この休暇制度を選択して導入する場合、以下の要件を満たす必要があります。
1.対象者
3歳から小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日)の子どもを養育する従業員が対象です。有期契約労働者や短時間労働者も対象に含まれますが、日雇い労働者は含まれません。
なお、以下の労働者については、労使協定を締結している場合に限り、企業は休暇の利用申出を拒むことができます。
- 継続して雇用された期間が1年未満のもの
2.付与日数・有効期間
1年につき10労働日以上を取得可能とする必要があります。有効期間は1年間で、起算日は企業が任意で決められます。
3.取得単位
養育両立支援休暇は、1日単位だけでなく、時間単位で取得可能とする必要があります。
時間単位で取得する場合、以下の取り扱いが必要です。
- 始業時刻から、または終業時刻まで連続して取得できるものとする。
- 1日に取得できる時間数は、休暇を取得する日の所定労働時間数に満たない範囲とします。
- 法令では、始業時刻や終業時刻と連続しない時間単位による取得(いわゆる中抜け)までは求められていません。ただし、厚生労働省の指針では、制度を柔軟に活用できるよう、中抜けを認めるなど配慮することが示されています。
4.取得理由
取得理由は、仕事と育児を両立しやすくするためであれば、用途は限定されません。例えば、保育所への送迎、授業参観や運動会などの学校行事の出席、就学予定の小学校の下見などが存在します。
実務上の重要なポイント
人事担当者が制度を運用するうえで、特に賃金や付与方法について注意が必要です。
1.賃金の取り扱い
賃金の取り扱い(有給・無給など)については、法令での定めはありません。企業の判断に委ねられます。ただし、勤務しなかった時間数を超えて賃金を減額することは禁じられています。
2.付与方法
「1年につき10労働日以上」であれば、1年単位で合計10労働日以上の休暇が付与されていれば問題ありません。例えば、6か月ごとに5日付与する、あるいは1か月ごとに1日付与するなど、分割して付与する方法も考えられます。
3.取得単位
年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定において、養育両立支援休暇の取得日を取得日を出勤とみなすかどうかは、企業が自由に決めることができます。
4.不利益な取扱いの禁止
養育両立支援休暇の取得を理由として、賞与や昇給等の査定・評価を下げることは、不利益な取扱いとして禁止されています。
他の育児関連休暇制度との比較
育児に関する休暇制度には、養育両立支援休暇のほかに、「育児目的休暇」や「子の看護等休暇」があります。これらの制度内容は一部重複する部分があるため、従業員からどの休暇を選択すべきか問い合わせが来る可能性があります。
混乱を避けるためにも、企業側でそれぞれの制度内容の違いや、3つの休暇制度の関係性を整理しておくことが重要です。
円滑な制度導入のためのステップ
養育両立支援休暇を円滑に導入するためには、以下のフローを参考に検討を進めることが重要です。
① 事前確認と措置の検討
まず、自社の既存の特別休暇制度や、仕事と子育ての両立に関するニーズ、企業の状況(業種、職種、方向性、課題など)を確認します。そのうえで、養育両立支援休暇を含む5つの措置のうち、自社にどの措置が適しているかを総合的に判断します。
既存の就業規則で特別休暇制度が導入されている場合、その制度内容を養育両立支援休暇の要件を満たすように整理・変更することで、柔軟な働き方を実現するための措置の一つとすることができます。
また、「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じようとする場合は、法令により、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴く必要があります。対象者だけでなく、管理職や周囲の従業員への影響も考慮し、バランスの取れた制度を目指しましょう。
② 養育両立支援休暇の導入決定
検討の結果、養育両立支援休暇の導入が適していると判断した場合、導入を決定します。なお、企業は先述の5つの措置のうち2つ以上を講じる必要があるため、養育両立支援休暇以外に、もう一つ以上の措置を選択・導入しなければなりません。
③ 社内ルールの決定
決定した措置について、養育両立支援休暇の要件を満たすように、休暇制度の内容や申出方法など、社内の運用方法を具体的に決定します。
④ 就業規則の変更・届出
自社が講じる2つ以上の措置の内容を明確にし、就業規則に規定します。
⑤ 社内への周知
制度導入の目的や背景だけでなく、運用方法についてもスムーズかつ適正に運?できるよう周知を徹底します。個別説明や所属長からの説明を行うなど、丁寧なフォローアップが望ましいです。また、休暇制度の内容に応じて、勤怠管理システムや給与計算システムの設定変更も必要です。
導入がもたらす企業メリットとご相談窓口

養育両立支援休暇の導入は、従業員にとって仕事と育児を両立しやすい職場環境を整える大きな一歩となります。
特に時間単位での取得が可能となることで、従業員は保育所や学校行事への参加、突発的な育児対応などにも柔軟に対応でき、安心して仕事を継続できます。
その結果、優秀な人材の離職防止や定着率向上につながり、従業員のモチベーションと生産性の向上、ひいては企業の発展に貢献することが期待されます。
2025年10月からの義務化を前に、自社の就業規則の確認、複数の措置の選択、そして従業員代表への意見聴取など、実務で対応すべき事項は多岐にわたります。
当法人では、育児・介護休業法の改正対応に関する企業の状況確認から、就業規則の変更、導入後の円滑な運用支援まで、一貫したサポートを提供しております。
「自社に最適な『柔軟な働き方を実現するための措置』をどう選定すべきか分からない」「就業規則の変更手続きに不安がある」といったお悩みをお持ちの中小企業経営者様、人事担当者様は、ぜひ一度、当社会保険労務士法人にご相談ください。
貴社の法令遵守と、働きがいのある職場づくりを、専門家として強力にサポートいたします。
個別相談・お問い合わせはこちらから
特に時間単位での取得が可能となることで、従業員は保育所や学校行事への参加、突発的な育児対応などにも柔軟に対応でき、安心して仕事を継続できます。
その結果、優秀な人材の離職防止や定着率向上につながり、従業員のモチベーションと生産性の向上、ひいては企業の発展に貢献することが期待されます。
2025年10月からの義務化を前に、自社の就業規則の確認、複数の措置の選択、そして従業員代表への意見聴取など、実務で対応すべき事項は多岐にわたります。
当法人では、育児・介護休業法の改正対応に関する企業の状況確認から、就業規則の変更、導入後の円滑な運用支援まで、一貫したサポートを提供しております。
「自社に最適な『柔軟な働き方を実現するための措置』をどう選定すべきか分からない」「就業規則の変更手続きに不安がある」といったお悩みをお持ちの中小企業経営者様、人事担当者様は、ぜひ一度、当社会保険労務士法人にご相談ください。
貴社の法令遵守と、働きがいのある職場づくりを、専門家として強力にサポートいたします。
個別相談・お問い合わせはこちらから