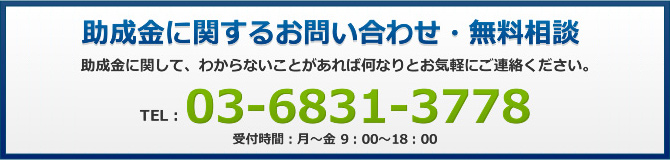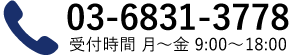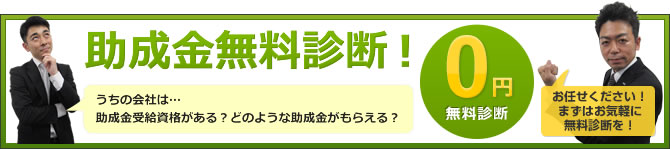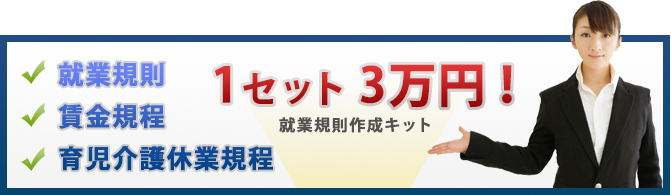従業員代表の選出、正しくできていますか?役割や民主的な選出方法、企業の義務を徹底解説
更新日:2025/09/16
労務管理

近年、働く人々のメンタルヘルス対策の重要性がますます高まっています。特に、長時間労働や職場のハラスメントなどが原因で精神的な不調を抱える労働者が増加している状況を踏まえ、労働安全衛生法等の改正が進められています。
これまで従業員数50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェック制度ですが、2025年5月に改正労働安全衛生法案が可決され、今後従業員数50人未満の事業場にも義務化される見通しとなりました。これは、多くの中小企業にとって、新たな対応が求められる重要な変更点です。
本コラムでは、中小企業におけるストレスチェック義務化について、その背景や制度の概要、企業が直面しうる課題、そして今から準備すべき対応策について、提供されたソースに基づいて詳しく解説します。
従業員代表とは?なぜ重要なのか
従業員代表とは、法令で定められた方法によって選出された、事業場の従業員の過半数を代表する者を指します。
事業場に、従業員の過半数で組織された労働組合がない場合、会社が従業員と「労使協定」を結んだり、「就業規則」を作成・変更したりする際には、この従業員代表の選出が不可欠です。
労務担当者の方は、従業員代表の選出手続きを正しく理解しておくことが非常に重要です。もし選出方法に不備があると、締結した労使協定が無効になるなどのリスクが生じる可能性があるため、注意が必要です。
この記事では、従業員代表の役割から正しい選出方法まで、分かりやすく解説します。
従業員代表が担う2つの主な役割
従業員代表は、従業員全体の意見を取りまとめて会社側と協議する重要な役割を担います。主な役割は以下の2つです。
- 労使協定の締結:労使協定とは、会社と従業員代表が話し合い、合意した内容を書面で締結するものです。時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)などがこれにあたります。
- 就業規則の作成・変更時における意見書の提出:就業規則は、労働時間や賃金といった労働条件や、従業員が守るべき職場の規律などを定めたものです。会社が就業規則を作成・変更する際には、従業員代表から内容に関する意見を聴き、その意見を記した意見書を提出してもらう必要があります。
誰が従業員代表になれる?3つの必須条件
従業員代表になるためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 1.事業場の全従業員の過半数を代表していること:正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、その事業場で働くすべての従業員の過半数を代表している必要があります。
- 2.民主的な手続きで選出されていること:選出にあたっては、投票、挙手、回覧、従業員による話し合いといった民主的な方法で、全従業員の過半数の支持を得ていることが求められます。会社の指名など、使用者の意向によって選ばれた場合は、従業員代表とは認められません。
- 3.管理監督者でないこと:「管理監督者」とは、労働条件の決定など、労務管理において経営者と一体的な立場にある者を指します。部長や工場長といった役職名だけでなく、職務内容、責任や権限、勤務態様などの実態に基づいて判断されます。トラブルを避けるためにも、選出の際には管理監督者に該当する可能性のある人は候補者から外すことをお勧めします。
【重要】従業員代表の正しい選出方法
適正な手続きを踏まないと協定が無効になるリスク
従業員代表の選出手続きが適正に行われなかった場合、その代表者が締結した労使協定や、意見を聴取した就業規則の変更などが無効と判断される可能性があります。
例えば、不適切な手続きで選ばれた従業員代表と締結した36協定は無効です。その状態で従業員に法定外労働をさせると法令違反となり、罰則が科される恐れがあります。
具体的な選出の手順
従業員代表は、従業員の意思に基づいて選出されなければなりません。具体的な手順の例は以下の通りです。
- 候補者を募る:まず、従業員代表を選出する目的(どの労使協定の締結のためか等)を全従業員に明らかにし、候補者を募ります。候補者が出ない場合は、従業員同士の話し合いで推薦してもらう方法もあります。前述の通り、管理監督者は候補者になれません。 なお、本来は労使協定の締結など目的ごとに選出するのが原則ですが、実務上の煩雑さを考慮し、年に一度(例:36協定の締結時期など)複数の目的をまとめて定期的に選出することも可能です。
- 従業員代表を選出する:候補者の中から、全従業員(管理監督者も含む)の意思を確認して代表者を選出します。投票、挙手、回覧、話し合いといった方法で、候補者が全従業員の過半数から支持を得ることで、正式に従業員代表となります。 注意点として、メールなどで意思確認を行う際に、返信がない人を「賛成」とみなす方法は認められていません。電話や対面などで、必ず従業員本人の意見を直接確認する必要があります。
選出は「事業場単位」が原則
従業員代表の選出は「事業場単位」で行うのが原則です。本社、支店、工場などが物理的に異なる場所にある場合は、それぞれで従業員代表を選出しなければなりません。 また、同じ場所にあっても、例えば工場内の食堂や診療所のように、労働の実態や業態が大きく異なる部門は別の事業場とみなされ、それぞれで選出が必要になる場合があります。
ただし、出張所のように規模が著しく小さく、独立した事業場とは言えない場合は、直近上位の組織(本社や支店など)とまとめて一つの事業場として扱うこともあります。
企業が果たすべき従業員代表への義務
企業は従業員代表に対して、以下の義務を負います。
- 不利益な取扱いの禁止:企業は、従業員が従業員代表であること、なろうとしたこと、あるいは代表として正当な行為をしたことを理由に、賃金の減額、降格、解雇といった不利益な扱いをしてはなりません。
- 必要な配慮:企業は、従業員代表がその役割を円滑に遂行できるよう、必要な配慮を行う義務があります。例えば、従業員の意見を集約するためにイントラネットや社内メール、事務スペースを利用させるなどの配慮が求められます。
まとめ:適切な労務管理は専門家へご相談を

従業員代表は、労使協定の締結や就業規則の作成・変更において非常に重要な役割を担っています。従業員代表を適正な手続きで選出し、従業員の意見を経営に反映できる体制を整えることは、従業員が安心して働ける職場づくりに直結します。
「従業員代表の選出方法が自社のやり方で正しいか不安だ」「労務管理について法的な観点から見直しをしたい」など、人事労務に関するお悩みやご不明点がございましたら、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。専門家が貴社の状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。
個別相談・お問い合わせはこちらから
「従業員代表の選出方法が自社のやり方で正しいか不安だ」「労務管理について法的な観点から見直しをしたい」など、人事労務に関するお悩みやご不明点がございましたら、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。専門家が貴社の状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。
個別相談・お問い合わせはこちらから