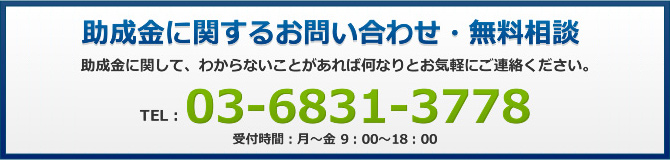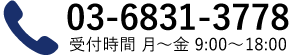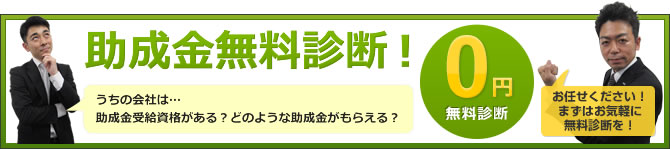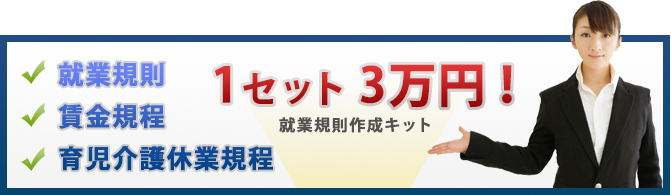【2025年6月義務化】職場熱中症対策、まだ間に合う!企業が取るべき「3つの義務」と従業員を守るポイント
更新日:2025/08/06
法改正

近年、働く人々のメンタルヘルス対策の重要性がますます高まっています。特に、長時間労働や職場のハラスメントなどが原因で精神的な不調を抱える労働者が増加している状況を踏まえ、労働安全衛生法等の改正が進められています。
これまで従業員数50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェック制度ですが、2025年5月に改正労働安全衛生法案が可決され、今後従業員数50人未満の事業場にも義務化される見通しとなりました。これは、多くの中小企業にとって、新たな対応が求められる重要な変更点です。
本コラムでは、中小企業におけるストレスチェック義務化について、その背景や制度の概要、企業が直面しうる課題、そして今から準備すべき対応策について、提供されたソースに基づいて詳しく解説します。
2025年6月から何が変わったのか?
毎年夏になると職場で多発する熱中症。厚生労働省の公表によると、2024年の職場における熱中症の死傷者数は1,257人、うち死亡者数は31人に上りました。このような痛ましい災害を防ぐため、労働安全衛生規則の改正に伴い、2025年6月1日から企業に対し熱中症対策が義務付けられました。
この法改正は、単なる努力義務ではなく、違反した場合には罰則が科される可能性があります。企業は従業員の安全を守るため、そして法的な責任を果たすため、この改正内容を正確に理解し、早急に対策を進める必要があります。本コラムでは、義務化される具体的な内容と、企業が今からでも取り組むべき予防策について詳しく解説します。
「熱中症」とは?その危険性を正しく理解する
熱中症とは、高温多湿な環境下で発汗による体温調整がうまく機能しなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。一般的な症状として、めまい、吐き気、意識障害などがあり、重症度はⅠ度からⅢ度に分類されます。Ⅰ度は軽度とされ現場での対応で改善が期待できますが、症状が改善しないⅡ度以降は医療機関への搬送が必要となります。
熱中症予防の指標として重要なのが「暑さ指数(WBGT値)」です。WBGT値が28度を超えると、熱中症患者が著しく増加するため特に注意が必要です。WBGT値は、人体と外気との熱のやりとりを考慮し、以下の3つの要素を取り入れています。
- 湿度
- 日射・輻射(ふくしゃ)などの周囲の熱環境
- 気温
熱中症は、屋外・屋内を問わず、暑い環境であればどこでも発症する可能性があるため、すべての業種・職種で対策が不可欠です。
【最重要】2025年6月1日施行!企業に義務化される「3つの対策」
2025年6月1日から企業に義務付けられる熱中症対策は、具体的に以下の「熱中症を発症するおそれのある作業」を行う場合に適用されます。
対象となる「熱中症を発症するおそれのある作業」とは?
これは、WBGT値が28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業を指します。この義務は、自社の従業員だけでなく、同一の場所で作業する協力会社の従業員など、従業員以外の人に対しても同様の措置が必要となります。
義務化された対策は、以下の3項目です。
1. 報告体制の整備
企業は、熱中症の自覚症状がある従業員、または熱中症のおそれがある従業員を発見した人が、その旨を報告するための体制を整備しなければなりません。そして、整備した体制を従業員に周知することが必須です。
具体的には、責任者の氏名、連絡先、連絡方法を明確に定め、従業員にいつでも報告できる状態を保つ必要があります。また、積極的に熱中症のおそれがある従業員を把握するため、以下の仕組みを構築することが推奨されます。
- 職場巡視
- バディ制度の採用(2人以上の従業員がお互いの健康状態を確認できる体制)
- ウェアラブルデバイスの活用(他の方法と組み合わせることが望ましい)
- 責任者と従業員双方での定期連絡
2. 手順書の作成
万が一熱中症が疑われる事態が発生した場合に備え、どのような実施手順で対応するかを明確にした手順書を作成する必要があります。緊急連絡網や、搬送先となる医療機関の連絡先(所在地を含む)を手順書に含めることが望ましいとされています。
実際の作成にあたっては、作業場所や作業内容の実態を踏まえ、それぞれの事業場に合った独自の手順を定めても問題ありません。
3. 関係者への周知
整備した報告体制と作成した手順書は、関係する従業員全員に確実に周知しなければなりません。周知方法としては、単独または複数組み合わせた方法が推奨されています。
- 事業所の見やすい場所への掲示
- メールでの通知
- 文書の配布
- 朝礼での伝達
また、緊急連絡先を従業員が見やすい場所に掲示することも効果的です。
義務化以前から取り組むべき!職場でできる熱中症予防対策
法改正による義務化だけでなく、日頃からの予防策も極めて重要です。ここでは、職場でできる具体的な熱中症予防策をご紹介します。
作業環境の工夫と休憩場所の確保
WBGT値が高い時には単独作業を控え、WBGT値に応じた作業の中止や、こまめな休憩取得などの工夫が必要です。特に気温が高くなる11時台から15時台は熱中症の死傷者数が多く発生しているため、屋外作業を避けるか、休憩の取り方を工夫することが推奨されます。作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所や日陰のある涼しい休憩場所を確保し、作業時間の短縮を検討することも有効です。
通気性の良い服装の着用
通気性の良い作業着を準備し、冷却機能を備えた衣服の着用も熱中症対策に繋がります。
汗で不足しがちな塩分と水分の補給
休憩場所に飲料水や塩飴などを常備しましょう。大量に発汗すると体内の塩分が失われるため、水分補給だけでは不十分です。水分と塩分の両方を補給することが大切であり、喉が渇いていなくても定期的に補給するよう促してください。スポーツ飲料や経口補水液を利用する場合は、製品ごとの「栄養成分表示」を確認し、成分量を把握しておくことをおすすめします。
従業員の健康観察と体調管理
管理者は従業員の異変に気づけるよう、日頃から健康観察や安全確保を行うことが重要です。初期症状が出ていても無理に仕事を続け、重症化するケースがあるため、「いつもと違う」と感じたら熱中症を疑う意識を持つことが大切です。熱中症「応急手当」カードなどの活用も有効でしょう。
また、熱中症は体調不良や不摂生、睡眠不足で発症リスクが高まります。発症の原因が本人の体調による要素が大きい場合、労災認定されない可能性もあるため、従業員は日常的に自身の体調管理に努める必要があります。朝礼時や作業前に活用できる「熱中症予防のための体調自己チェックリスト」の利用も推奨されます。
特に配慮が必要な高齢従業員への対策
高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、体温を下げる身体反応が弱まっていることがあります。昔と比べて異常な暑さとなっている昨今、高齢の従業員の体調変化を観察し、体調確認や水分補給などの積極的な声かけを心がけましょう。
従業員自身の体調管理も重要です
企業による対策だけでなく、従業員一人ひとりが自身の健康管理を意識することも非常に重要です。熱中症の危険性や、簡単にできるセルフケアの方法などを従業員に周知することで、職場全体の熱中症リスクを効果的に防ぐことができます。
安全な職場環境の実現へ。熱中症対策は専門家にお任せください!
高齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、体温を下げる身体反応が弱まっていることがあります。昔と比べて異常な暑さとなっている昨今、高齢の従業員の体調変化を観察し、体調確認や水分補給などの積極的な声かけを心がけましょう。
従業員自身の体調管理も重要です
企業による対策だけでなく、従業員一人ひとりが自身の健康管理を意識することも非常に重要です。熱中症の危険性や、簡単にできるセルフケアの方法などを従業員に周知することで、職場全体の熱中症リスクを効果的に防ぐことができます。
安全な職場環境の実現へ。熱中症対策は専門家にお任せください!

2025年6月からの法改正により、職場の熱中症対策は「義務」となります。しかし、多岐にわたる対策を漏れなく、かつ自社の状況に合わせて実施していくことは容易ではありません。
当社会保険労務士法人は、義務化される報告体制の整備、手順書の作成、周知徹底について、お客様の事業所の実態に合わせた具体的なコンサルティングを提供いたします。労務管理のプロフェッショナルとして、貴社が従業員の安全を守り、法改正に適切に対応できるよう、強力にサポートいたします。
熱中症対策に関するご相談や、具体的な対策の進め方についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当社会保険労務士法人までお問い合わせください。
個別相談・お問い合わせはこちらから
当社会保険労務士法人は、義務化される報告体制の整備、手順書の作成、周知徹底について、お客様の事業所の実態に合わせた具体的なコンサルティングを提供いたします。労務管理のプロフェッショナルとして、貴社が従業員の安全を守り、法改正に適切に対応できるよう、強力にサポートいたします。
熱中症対策に関するご相談や、具体的な対策の進め方についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に当社会保険労務士法人までお問い合わせください。
個別相談・お問い合わせはこちらから