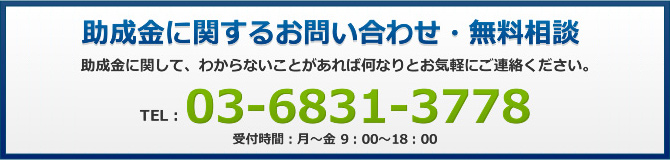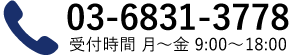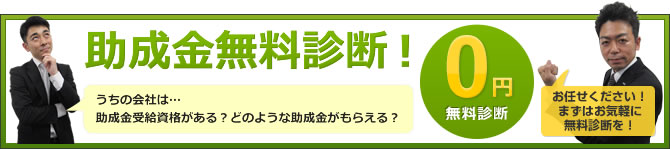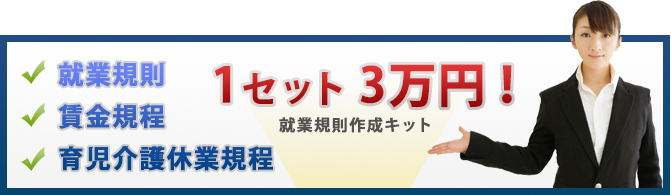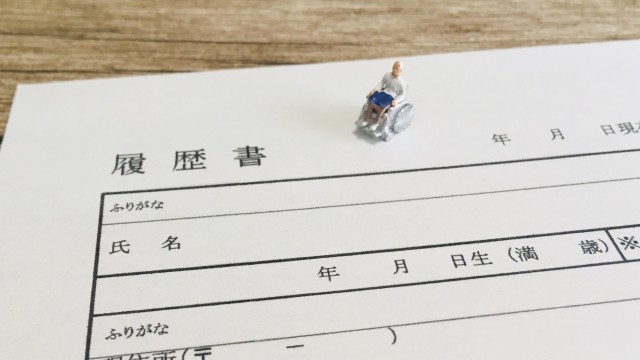【社労士解説】中小企業が知っておくべき女性従業員の妊娠・出産に関わる法令と会社の対応|人材定着のために
更新日:2025/07/08
労務管理

近年、働く人々のメンタルヘルス対策の重要性がますます高まっています。特に、長時間労働や職場のハラスメントなどが原因で精神的な不調を抱える労働者が増加している状況を踏まえ、労働安全衛生法等の改正が進められています。
これまで従業員数50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェック制度ですが、2025年5月に改正労働安全衛生法案が可決され、今後従業員数50人未満の事業場にも義務化される見通しとなりました。これは、多くの中小企業にとって、新たな対応が求められる重要な変更点です。
本コラムでは、中小企業におけるストレスチェック義務化について、その背景や制度の概要、企業が直面しうる課題、そして今から準備すべき対応策について、提供されたソースに基づいて詳しく解説します。
なぜ中小企業も女性従業員の妊娠・出産時の対応を知るべきか?
近年、妊娠中や出産後も働く女性従業員が増加しています。少子高齢化が進む日本において、従業員が安心して子どもを産み育てられる環境を整えることは、社会全体にとって重要であるだけでなく、貴重な人材を確保し、会社に長く定着してもらうためにも、企業にとって非常に大切な課題となっています。
女性従業員が妊娠・出産を迎えるにあたり、企業が理解しておくべき法令や対応があります。これらを正しく理解し、適切な対応を取ることは、従業員の安心につながり、結果として優秀な人材の離職を防ぐことにもつながります。
今回の記事では、特に中小企業の経営者様やご担当者様が知っておくべき、女性従業員の妊娠・出産に関わる主要な法令と、具体的に会社が取るべき対応について解説します。
男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理の義務
男女雇用機会均等法には、妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員を対象に、企業の義務として定められている「母性健康管理」に関する規定があります。これは、母体や胎児の健康を守りながら、女性従業員が安心して働き続けられるようにするためのものです。
具体的には、以下の措置を講じる必要があります。
健康診査等を受ける時間の確保
妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員は、健康診査や保健指導を受ける必要があります。企業は、 女性従業員がこれらの受診に必要な時間を確保できるよう、申し出があったときに時間を確保することが義務付けられています。
対象となる健康診査等
本人を対象とする産科に関する診察・検査や、その結果に基づく個別の保健指導です。両親学級のような集団の保健指導についても、本人が希望する場合は可能な限り受診できるよう配慮することが望ましいとされています。
確保すべき時間
受診そのものの時間だけでなく、医療機関での待ち時間や移動時間など、受診に必要な前後の時間を含めて確保することが求められています。
確保すべき回数
原則として、以下の回数を確保する必要があります。ただし、医師等からこれと異なる指示があった場合は、その指示に従います。
- 妊娠23週まで:4週間に1回
- 妊娠24週から35週まで:2週間に1回
- 妊娠36週から出産まで:1週間に1回
- 出産後(1年以内):医師等が必要と認める回数
※「健康診査」と「結果に基づく保健指導」を合わせて1回とカウントするため、これらが同日に行われない場合は2日間の確保が必要です。
確保するための方法
通院先の医療機関や通院日は原則として本人の希望で決定します。申請方法(書面、口頭など)や、取得単位(半日、1時間など)は企業が定めることができますが、その際は労使で話し合うことが望ましいとされています。厚生労働省が申請様式を公開していますので、参考にすると良いでしょう。
医師等からの指導事項を守るための措置
妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員が、医師等から勤務について具体的な指導を受けた場合、企業はその指導事項に従った措置を講じることが義務付けられています。措置を決定した際は、速やかに本人へ内容を明示する必要があります(書面での明示が推奨されています)。
具体的な指導内容と措置の例は以下の通りです。
① 通勤緩和の措置
医師等から通勤に関する指導を受けた場合、女性従業員がラッシュアワーの混雑を避けて通勤できるよう措置を取る必要があります。
【具体的な措置の例】
- 時差出勤(30~60分程度の時間差出勤・退勤、フレックスタイム制の導入)
- 勤務時間の短縮(30~60分程度の短縮
- 交通手段・通勤経路の変更(交雑の少ない経路への変更など
- 公共交通機関だけでなく、自家用車通勤務対象となり得ます。
② 休憩に関する措置
医師等から休憩に関する指導を受けた妊娠中の女性従業員からの申し出があった場合、女性従業員の状況に応じて休養や補食ができるよう措置を取る必要があります。
【具体的な措置の例】
休憩時間の延長、休憩回数の増加、休憩時間帯の変更など。個人の健康状態や仕事内容に合わせ、産業医などの産業保健スタッフと相談しながら個別の状況を踏まえた措置を検討・実施することが推奨されています。
③ 妊娠中または出産後の症状等に対応する措置
医師等から症状等について指導を受けた女性従業員からの申し出があった場合、医師等の指導に基づき措置を取る必要があります。これは、妊娠中だけでなく、出産後1年以内の女性従業員も対象となります。
【具体的な措置の例】
作業の制限、勤務時間の短縮、休業など。
なお、勤務しなかった時間や短縮した時間の賃金の支払いは法律上の義務ではありません。無給とすることも差し支えありませんが、女性従業員が安心して指導事項を申し出られるように、有給での取り扱いも検討することが推奨されています。
医師等の指導が不明確な場合の対応
医師等からの指導が具体的でない場合や、症状等に対応する措置内容が不明確なケースも発生します。女性従業員から、医師等から妊娠の経過に異常やその恐れについて指導を受けた旨の申し出があったにもかかわらず、指導内容が不明確な場合は、企業は以下の対応を取る必要があります。
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)の活用
企業が母性健康管理の措置に適切に対応するためには、医師等からの指導内容が的確かつ明確であることが重要です。そのための有効なツールとして、医師等に記入してもらう「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」の利用が推奨されています。
このカードを女性従業員が企業へ提出した場合、企業は記入された内容に沿った措置を取らなければなりません。カードはあくまで手段であり、カードの提出の有無に関わらず、医師等からの指導があった場合にはそれに沿った措置を講じる必要があります。
母健連絡カードの表面には、女性従業員の氏名や指示事項、措置が必要な期間などが記載されます。裏面には、各症状に対して企業で行うことができる措置の例が記載されています。厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。
なお、従業員の健康状態に関する情報はプライバシーに属する情報です。母性健康管理の措置を運用する際は、プライバシーの保護に十分配慮する必要があります。
労働基準法による母性保護
労働基準法にも、妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員を対象とした母性保護に関する定めがあります。
例えば、女性従業員から請求があった場合に、法定の産前・産後休業を与える義務や、危険有害業務への就業制限などがあります。また、妊娠中の女性が請求した場合、軽易な業務への転換をさせる義務も定められています。これらの規定は、女性従業員の請求の有無にかかわらず、企業が対応しなければならない項目も含まれています。
妊娠・出産等に関する不利益取扱いの禁止とハラスメント防止
男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置や、労働基準法による母性保護措置等を利用したことなどを理由とする、解雇その他の不利益な取り扱いは法律で禁止されています。
「不利益な取扱い」とは、妊娠したこと、出産したこと、あるいは妊娠・出産に関係する制度(母性健康管理措置、産前産後休業、育児休業など)を利用したこと等を理由として、降格や減給、不利益な配置転換、契約更新をしないといった扱いをすることを指します。
また、企業には、上司や同僚による妊娠・出産等に関するハラスメント(いわゆるマタニティハラスメントなど)を防ぐための措置を講じることも求められています。
これらの不利益取扱いを行ったり、ハラスメントの防止措置を適切に講じなかった場合、企業の名称公表や罰則の適用を受ける可能性があります。
まとめ:法令理解と適切な対応で人材定着へ
女性従業員の妊娠・出産に関する法令や対応は多岐にわたります。単に法令を遵守するというだけでなく、適切な母性健康管理や母性保護を行うことは、女性従業員が安心してキャリアを継続できる環境を作り、優秀な人材の定着につながります。
また、2024年11月施行の「フリーランス・事業者間取引適正化等法」では、業務委託の発注者にも育児等との両立への配慮義務やハラスメント対応が求められるようになるなど、母性健康管理や母性保護の流れは、雇用という枠を超えて社会全体に広がっています。中小企業も、これらの社会的な課題に注目し、対応を検討していく必要があります。
女性従業員の妊娠・出産に関わる労務管理は専門家にご相談ください

女性従業員の妊娠・出産に際して、企業が取るべき対応は、従業員の状況や会社の規定によって様々です。法令遵守はもちろんのこと、従業員が安心して働き続けられる環境を整備するためには、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。
日本社労士法人では、中小企業の皆様が直面する女性従業員の妊娠・出産に関わる様々な労務管理について、個別のご相談に応じております。法改正への対応、社内規程の整備、従業員への説明方法、具体的な休業や措置の取り方など、貴社の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
女性従業員の妊娠・出産に関わる労務管理でお悩みがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。貴社の大切な人材が安心して活躍できる職場づくりを、専門家の視点から支援いたします。
個別相談・お問い合わせはこちらから