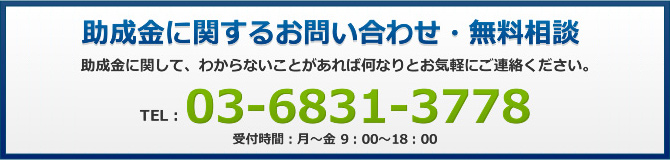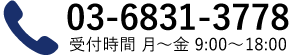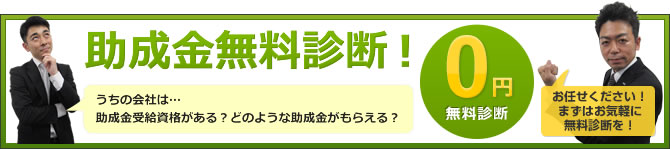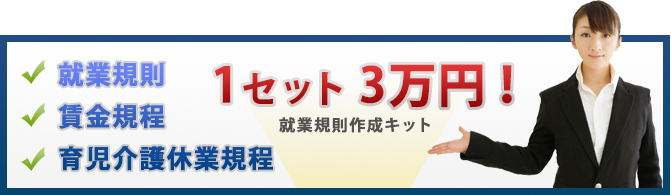【社労士解説】中小企業が知っておくべき高齢者・障害者雇用のルールとメリット|2026年法定雇用率引き上げに備える
更新日:2025/07/08
労務管理
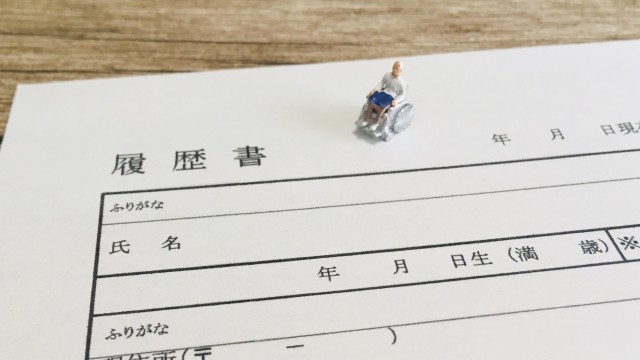
近年、働く人々のメンタルヘルス対策の重要性がますます高まっています。特に、長時間労働や職場のハラスメントなどが原因で精神的な不調を抱える労働者が増加している状況を踏まえ、労働安全衛生法等の改正が進められています。
これまで従業員数50人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェック制度ですが、2025年5月に改正労働安全衛生法案が可決され、今後従業員数50人未満の事業場にも義務化される見通しとなりました。これは、多くの中小企業にとって、新たな対応が求められる重要な変更点です。
本コラムでは、中小企業におけるストレスチェック義務化について、その背景や制度の概要、企業が直面しうる課題、そして今から準備すべき対応策について、提供されたソースに基づいて詳しく解説します。
なぜ今、中小企業も高齢者・障害者雇用を知る必要があるのか?
日本の少子高齢化が進む中で、働く意欲のある高齢者や障害を持つ方々が活躍できる社会の実現が強く求められています。これにより、企業における高齢者や障害者の雇用は今後ますます増加することが予想されています。
一定数以上の従業員を雇用する企業には、毎年6月1日時点での高齢者および障害者の雇用状況を報告することが法令等で義務付けられています。さらに、法令に基づいて、企業は高齢者の雇用確保や障害者の雇用促進に取り組む必要があります。
これらの雇用に関するルールは、企業規模にかかわらず適用されるものもあり、中小企業も決して無関係ではありません。特に、2026年7月には、障害者の法定雇用率が現在の2.5%から2.7%に引き上げられるとともに、障害者を雇用する義務がある企業の対象が、従業員40.0人以上から37.5人以上に拡大する予定です。これは、これまで障害者雇用義務の対象外だった企業も、新たに対象となる可能性があることを意味します。
法令を遵守することはもちろんですが、高齢者や障害者の雇用は、人材不足対策や企業イメージ向上など、中小企業にとって多くのメリットをもたらす可能性も秘めています。変化する雇用環境に対応するためにも、中小企業経営者の皆様には、高齢者・障害者雇用に関する最新の情報を把握しておくことが重要です。
「高齢者雇用」のルール|65歳までの義務と70歳までの努力義務
高齢者の雇用については、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」に基づいて定められています。
65歳までの雇用確保措置(義務)
現在、定年を65歳未満に定めている企業は、従業員が希望すれば65歳まで安定して働けるよう、以下のいずれかの措置を講じることが法律で義務付けられています。
- ① 定年制の廃止
- ② 定年の引き上げ
- ③ 継続雇用制度の導入
2024年の集計結果では、ほぼ全ての企業(99.9%)がこれらの措置を実施しています。措置の内容としては、継続雇用制度の導入が最も多く67.4%を占めています。また、希望者全員を対象とする継続雇用制度を導入している企業は86.2%あり、前年よりも増加しています。
70歳までの就業確保措置(努力義務)
さらに高年齢者雇用安定法では、65歳から70歳まで就業機会を確保するため、企業に対し以下のいずれかの措置を講ずるよう「努力義務」を求めています。これは、70歳までの定年引き上げを義務付けるものではありません。対象となるのは、定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている企業や、継続雇用制度を導入している企業です。
- ① 70歳までの定年引き上げ
- ② 70歳までの継続雇用制度の導入
- ③ 創業支援等措置(フリーランス契約による業務委託など、雇用以外の形で支援する措置)
- ④ 社会貢献事業への参加支援
- ⑤ その他
2024年の集計では、70歳までの就業確保措置を実施している企業は全体の31.9%であり、前年より2.2ポイント増加しています。中小規模の企業(従業員21人以上300人以下)では32.4%が実施しており、比較的高い実施率となっています。措置内容としては、継続雇用制度の導入が25.6%と最も多くなっています。
定年制の現状と高齢者雇用における注意点
企業の定年制については、定年を65歳以上とする企業が全体の32.6%を占めており、「60歳」とする企業が減少する一方で、「61?64歳」「65歳」「70歳以上」とする企業が増加傾向にあります。
今後ますます高年齢の従業員が増える中で、企業は働く環境にも配慮が必要です。高齢の従業員は、ほかの世代と比較して労働災害の発生率が高く、休業が長期化しやすいという特徴があるため、労働災害を発生させないための職場環境改善などに優先的に取り組むことが求められます。厚生労働省の「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」には、企業が取り組むべき5項目が挙げられていますので、参考にすると良いでしょう。
「障害者雇用」のルール|法定雇用率と対象企業、そして2026年の変更点
障害者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」に基づいて定められています。この法律では、企業に法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務を定めています。
法定雇用率と現在の義務対象企業
現在の民間企業の法定雇用率は2.5%です。これは、従業員を40.0人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用する義務があることを意味します。
2024年6月1日現在、民間企業で雇用されている障害者数は過去最高を記録しており、特に精神障害者の伸び率が大きくなっています。これは法定雇用率が2.3%から2.5%へ上昇した影響も含まれています。
しかし、法定雇用率を達成できていない企業は全体の64.1%と半数以上を占めており、そのうち障害者を1人も雇用していない「0人雇用企業」が57.6%を占めているという現状もあります。
2026年7月からの変更点
繰り返しになりますが、2026年7月からは、障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられます。さらに、障害者雇用が義務付けられる企業の対象が、現在の従業員40.0人以上から、従業員37.5人以上の企業に拡大されます。
これにより、これまで障害者雇用義務の対象ではなかった従業員37.5人~39.9人の企業も、新たに義務対象となる可能性があります。自社の従業員数を改めて確認し、対象となるか、また今後対象となりそうかを確認しておくことが重要です。
高齢者・障害者雇用を進めるメリット
法令遵守のために雇用を進めるだけでなく、高齢者や障害者の雇用には、企業にとって以下のような多くのメリットがあると言われています。
- 人手不足の解消につながる:働く意欲のある高齢者や障害者の方を迎え入れることで、人手不足の解消につながり、貴重な戦力を確保できます。
- 社内の生産性向上や業務改善につながる:障害の特性を活かした育成や、障害を持つ従業員がスムーズに仕事できるよう業務プロセスを見直す中で、思わぬ無駄が省かれ、結果として社内全体の生産性向上につながる場合があります。
- 社内コミュニケーションの活性化:多様なバックグラウンドを持つ従業員が働く中で、お互いを理解し、配慮し合う姿勢が浸透し、社内のコミュニケーションが活発になることが期待できます。
- 企業イメージの向上:高齢者や障害者雇用に積極的に取り組む企業は、社会的な責任を果たしている企業として、対外的なイメージが向上します。
中小企業が今すぐ取り組むべきこと
今後ますます重要となる高齢者・障害者雇用に向けて、中小企業が今から準備しておくべきことは何でしょうか。
1.自社の現状把握
- 従業員数、年齢構成、定年制を確認しましょう。
- 障害者の雇用状況を確認しましょう。
2.法令遵守の確認
- 現在の法令(65歳までの雇用確保措置の実施、法定雇用率の達成状況)を満たしているか確認しましょう。
- 特に2026年7月からの障害者雇用義務の対象となるか、従業員数を確認しましょう。
3.今後の人事計画への反映
- 定年を迎える従業員の雇用継続について、本人との話し合いや制度の周知を進めましょう。
- 障害者雇用が義務対象となる場合、どのような業務で障害者を雇用できるか、社内の体制はどうするかなどを検討し始めましょう。
4.専門家への相談も検討
- 高齢者雇用や障害者雇用に関する制度設計、助成金活用、安全な職場づくり、具体的な募集・選考方法など、不明な点や不安がある場合は、専門家である社会保険労務士に相談することを検討しましょう。
高齢者・障害者雇用について、専門家にご相談ください

高齢者・障害者雇用は、単なる法改正への対応ではなく、企業の持続的な成長と多様な人材の活用にとって重要な経営課題です。しかし、「具体的な対応方法が分からない」「自社の場合、何から着手すれば良いか」といった疑問をお持ちの中小企業経営者様もいらっしゃるかと思います。
日本社労士法人では、中小企業の皆様の状況に合わせた、社内規程の作成・変更、労働環境整備に関するアドバイス、各種助成金の情報提供など、幅広いサポートを提供しております。
法改正への対応や、より積極的な高齢者・障害者雇用にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
個別相談・お問い合わせはこちらから